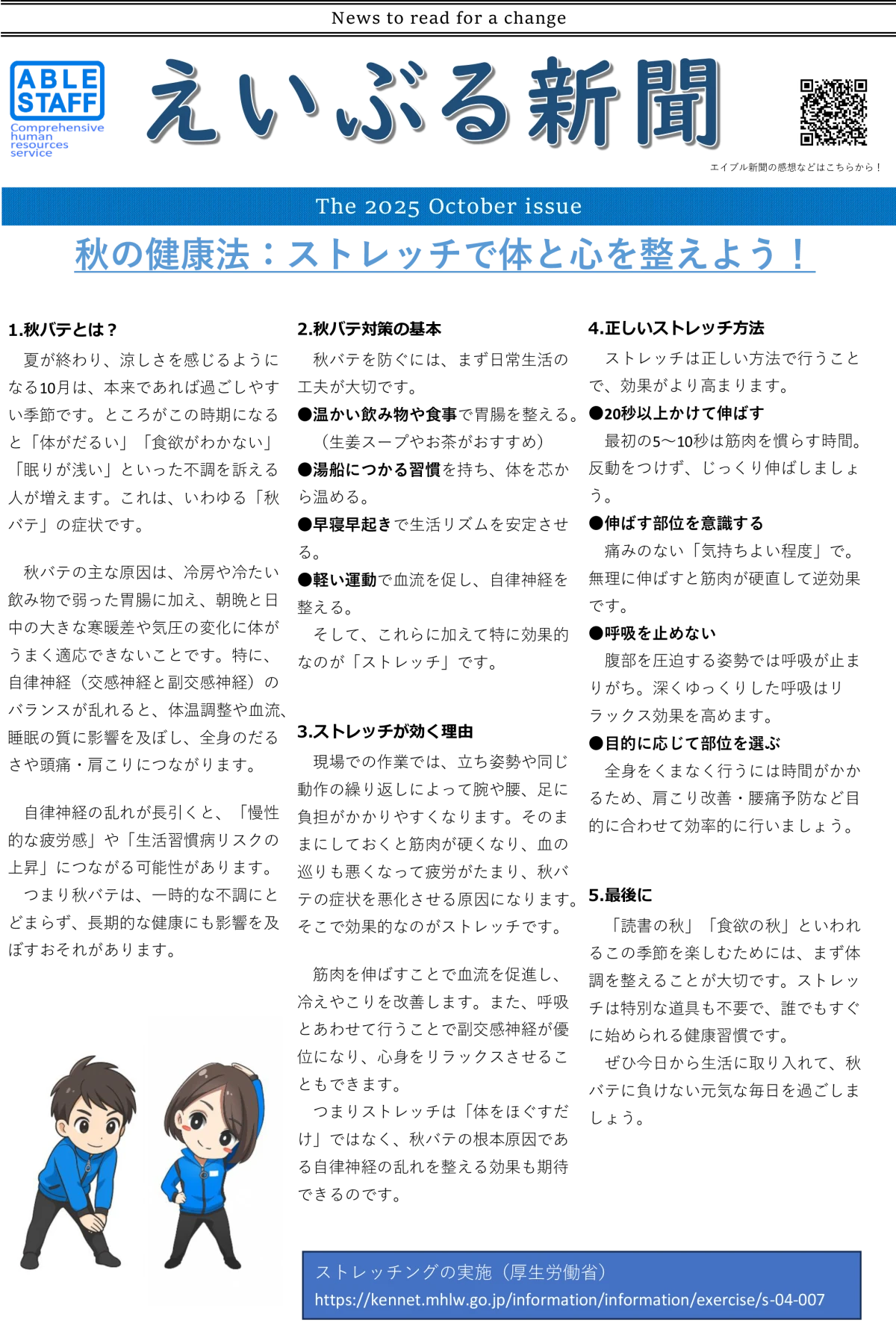
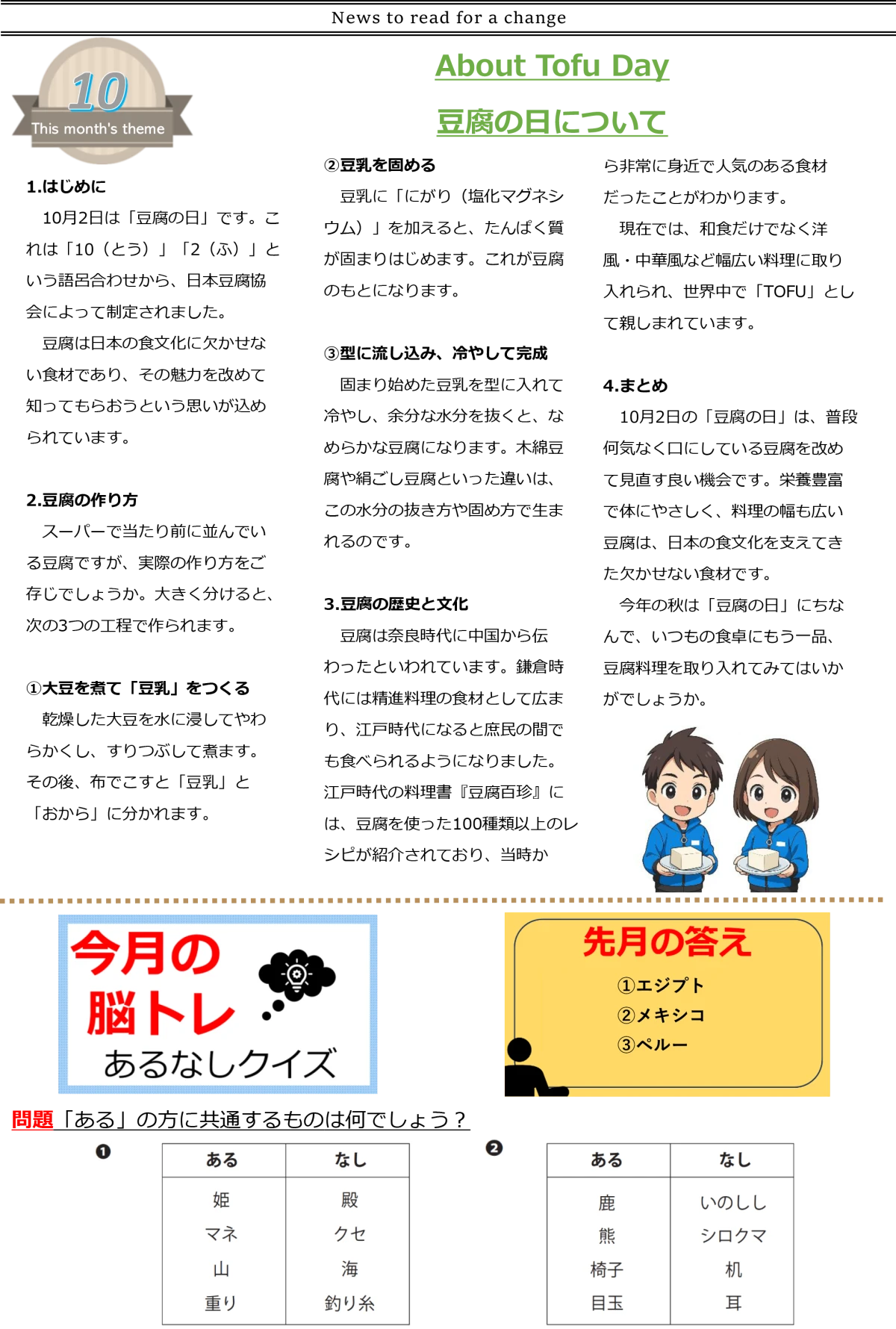
秋の健康法:ストレッチで体と心を整えよう!
1.秋バテとは?
夏が終わり、涼しさを感じるようになる10月は、本来であれば過ごしやすい季節です。
ところがこの時期になると「体がだるい」「食欲がわかない」「眠りが浅い」といった不調を訴える人が増えます。
これは、いわゆる「秋バテ」の症状です。
秋バテの主な原因は、冷房や冷たい飲み物で弱った胃腸に加え、朝晩と日中の大きな寒暖差や気圧の変化に体がうまく適応できないことです。
特に、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが乱れると、体温調整や血流、睡眠の質に影響を及ぼし、全身のだるさや頭痛・肩こりにつながります。
自律神経の乱れが長引くと、「慢性的な疲労感」や「生活習慣病リスクの上昇」につながる可能性があります。
つまり秋バテは、一時的な不調にとどまらず、長期的な健康にも影響を及ぼすおそれがあります。
2.秋バテ対策の基本
秋バテを防ぐには、まず日常生活の工夫が大切です。
●温かい飲み物や食事で胃腸を整える。
(生姜スープやお茶がおすすめ)
●湯船につかる習慣を持ち、体を芯から温める。
●早寝早起きで生活リズムを安定させる。
●軽い運動で血流を促し、自律神経を整える。
そして、これらに加えて特に効果的なのが「ストレッチ」です。
3.ストレッチが効く理由
現場での作業では、立ち姿勢や同じ動作の繰り返しによって腕や腰、足に負担がかかりやすくなります。
そのままにしておくと筋肉が硬くなり、血の巡りも悪くなって疲労がたまり、秋バテの症状を悪化させる原因になります。
そこで効果的なのがストレッチです。
筋肉を伸ばすことで血流を促進し、冷えやこりを改善します。
また、呼吸とあわせて行うことで副交感神経が優位になり、心身をリラックスさせることもできます。
つまりストレッチは「体をほぐすだけ」ではなく、秋バテの根本原因である自律神経の乱れを整える効果も期待できるのです。
4.正しいストレッチ方法
ストレッチは正しい方法で行うことで、効果がより高まります。
ストレッチングの実施(厚生労働省)
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/exercise/s-04-007
5.最後に
「読書の秋」「食欲の秋」といわれるこの季節を楽しむためには、まず体調を整えることが大切です。
ストレッチは特別な道具も不要で、誰でもすぐに始められる健康習慣です。
ぜひ今日から生活に取り入れて、秋バテに負けない元気な毎日を過ごしましょう。
About Tofu Day 豆腐の日について
1.はじめに
10月2日は「豆腐の日」です。
これは「10(とう)」「2(ふ)」という語呂合わせから、日本豆腐協会によって制定されました。
豆腐は日本の食文化に欠かせない食材であり、その魅力を改めて知ってもらおうという思いが込められています。
2.豆腐の作り方
スーパーで当たり前に並んでいる豆腐ですが、実際の作り方をご存じでしょうか。
大きく分けると、次の3つの工程で作られます。
①大豆を煮て「豆乳」をつくる
乾燥した大豆を水に浸してやわらかくし、すりつぶして煮ます。
その後、布でこすと「豆乳」と「おから」に分かれます。
3.豆腐の歴史と文化
豆腐は奈良時代に中国から伝わったといわれています。
鎌倉時代には精進料理の食材として広まり、江戸時代になると庶民の間でも食べられるようになりました。
江戸時代の料理書『豆腐百珍』には、豆腐を使った100種類以上のレシピが紹介されており、当時から非常に身近で人気のある食材だったことがわかります。
現在では、和食だけでなく洋風・中華風など幅広い料理に取り入れられ、世界中で「TOFU」として親しまれています。
4.まとめ
10月2日の「豆腐の日」は、普段何気なく口にしている豆腐を改めて見直す良い機会です。
栄養豊富で体にやさしく、料理の幅も広い豆腐は、日本の食文化を支えてきた欠かせない食材です。
今年の秋は「豆腐の日」にちなんで、いつもの食卓にもう一品、豆腐料理を取り入れてみてはいかがでしょうか。
