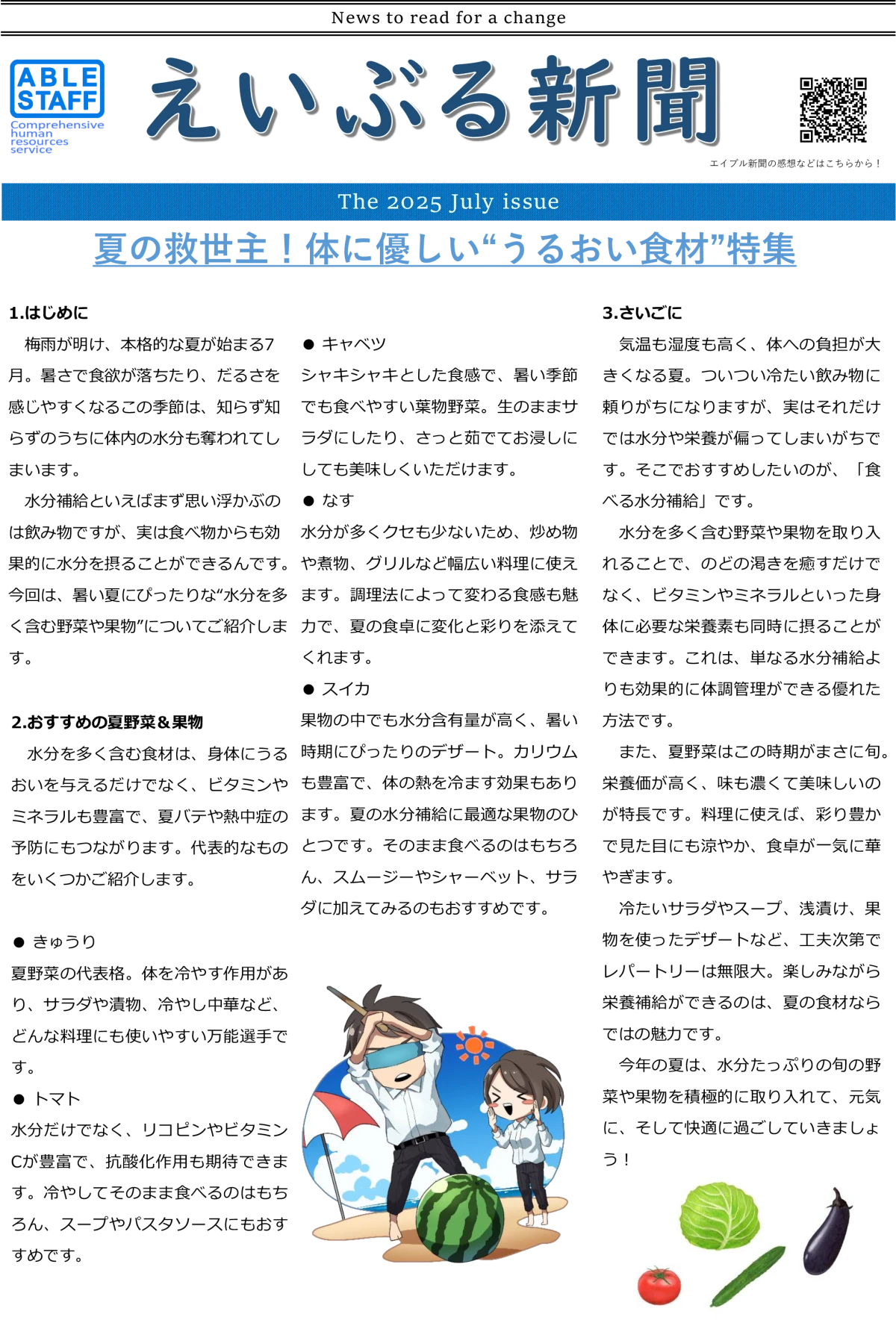

夏の救世主!体に優しい“うるおい食材”特集
1.はじめに
梅雨が明け、本格的な夏が始まる7月。
暑さで食欲が落ちたり、だるさを感じやすくなるこの季節は、知らず知らずのうちに体内の水分も奪われてしまいます。
水分補給といえばまず思い浮かぶのは飲み物ですが、実は食べ物からも効果的に水分を摂ることができるんです。
今回は、暑い夏にぴったりな“水分を多く含む野菜や果物”についてご紹介します。
2.おすすめの夏野菜&果物
水分を多く含む食材は、身体にうるおいを与えるだけでなく、ビタミンやミネラルも豊富で、夏バテや熱中症の予防にもつながります。
代表的なものをいくつかご紹介します。
3.さいごに
気温も湿度も高く、体への負担が大きくなる夏。
ついつい冷たい飲み物に頼りがちになりますが、実はそれだけでは水分や栄養が偏ってしまいがちです。
そこでおすすめしたいのが、「食べる水分補給」です。
水分を多く含む野菜や果物を取り入れることで、のどの渇きを癒すだけでなく、ビタミンやミネラルといった身体に必要な栄養素も同時に摂ることができます。
これは、単なる水分補給よりも効果的に体調管理ができる優れた方法です。
また、夏野菜はこの時期がまさに旬。栄養価が高く、味も濃くて美味しいのが特長です。
料理に使えば、彩り豊かで見た目にも涼やか、食卓が一気に華やぎます。
冷たいサラダやスープ、浅漬け、果物を使ったデザートなど、工夫次第でレパートリーは無限大。
楽しみながら栄養補給ができるのは、夏の食材ならではの魅力です。
今年の夏は、水分たっぷりの旬の野菜や果物を積極的に取り入れて、元気に、そして快適に過ごしていきましょう!
Origin of Marine Day 海の日の由来
1.はじめに
7月の第3月曜日は「海の日」。
2025年は 7月21日(月) です。
毎年カレンダーには載っているこの祝日ですが、「なぜ“海の日”があるのか?」と聞かれると、意外と詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな「海の日」の由来や意味、そして海との関わりについて、あらためてご紹介します。
2.海の日は何のための祝日?
「海の日」は、“海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日” として定められた、世界でも珍しい「海を祝う国民の祝日」です。
日本は四方を海に囲まれ、古くから漁業・貿易・交通など、さまざまな面で海と深い関係を築いてきました。
私たちの食卓に並ぶ魚や海藻、日々の輸出入に使われる船、海水浴やマリンスポーツといったレジャーに至るまで、生活のあらゆる場面に海の恵みが息づいています。
こうした海の存在とその恩恵に感謝しようという想いから、1996年に「海の日」は国民の祝日として制定されました。
3.最初は「7月20日」だった?
もともと「海の日」は7月20日と決められていました。
この日は、明治天皇が1876年に東北地方を巡幸された際、灯台視察船「明治丸」で横浜港に帰着された日にちなんでいます。
その後、2003年の「ハッピーマンデー制度(※)」により、現在の「7月第3月曜日」へと移動しました。
3連休になったことで、海や自然を親しむ機会として、家族や友人とレジャーを楽しむ人も少なくないようです。
※祝日を月曜日に移動させて三連休にする制度
3.最後に
気候変動や海洋ごみの問題など、今や海は私たちにとっての“癒し”だけでなく、“考えるべき課題”も抱える存在となっています。
だからこそ、こうした祝日に海について思いを巡らせることは、今の時代にとても大切なことではないでしょうか。
この「海の日」をきっかけに、海の美しさ、恩恵、そして守るべき環境について、少し意識を向けてみるのも良いかもしれません。
